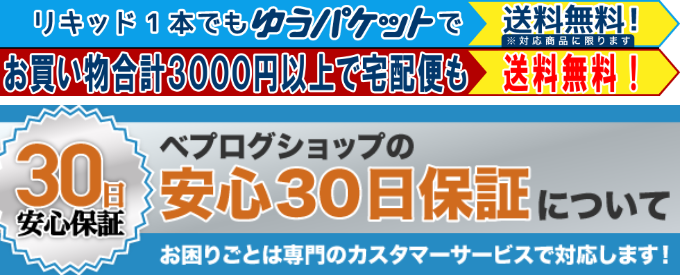Kaeesとフレキチを応援してVAPEを盛り上げよう
他のブログでもこのアトマイザーのレビューを目にすることが多いと思いますが、そこにはれっきとした理由があります。
今回ご紹介するRDAはKaees(ケイス←『ケイス』って読むみたいです。ずっと『キース』だと思っていました。)のAlexanderというRDAなのですが、Kaeesが行っている活動が日本のVAPE業界を盛り上げることにつながる可能性があるからです。
今、日本で販売されているVAPEの大部分は海外、特に中国から仕入れているものが多いようです。
メーカーから中間仕入れ業者を経由しているので、エンドユーザーである我々が支払う金額には、多少なりとも中間業者分の利益が上乗せされていることになります。
最近は国内VAPEショップの閉店が相次いでいますが、ショップ側の利益(体力)を削って我々に商品を販売してくれていたために、ショップ側が倒れてしまったと考えるのが普通でしょう。
そこで、Kaeesは考えました。
中間卸業者から直接販売店に卸してやれば、ショップも無理せず、もっとVAPE業界が活性化するんじゃね?
そんな考えから、日本ではフレキチさんを窓口にして日本にAlexander RDAを広めようとしてくれているのです。
「もっと多くの人と一緒にVAPEを楽しみたい」と思っている私にとっては、非常に応援したくなる内容でした。
この話を聞いて、Kaeesを応援したくなりましたし、より一層フレキチさんも応援したくなりました。
このRDAが気に入るかどうか、どこで手に入れるかどうかは置いておいて、Kaeesがしようとしてくれていること、フレキチさんがしようとしてくれていることをは知っておいてほしいなぁと思います。
では、さっそくAlexander RDAのレビューに入っていきましょう。
Alexander RDA付属品

- Alexander RDA本体
- 簡易マニュアル
- ミニ六角ドライバー
- イモネジ×4
- BFピン
- クラプトンコイル×2
- 交換用Oリング
付属品は必要なものが必要なだけ入っているといった印象。
コットンから何から付属品に入っていることがありますが、正直自分の気に入ったコットンを持っている人が多いので、ほぼ使ったことはありません。
Alexander RDAポジティブピン
通常コンタクトピン(デフォルト)

しっかりと飛び出たポジティブピンがデフォルトでインストールされています。
メカでの使用の際も、十分使用に耐えうる出代かと思います。
BFピン

BFピンに付け替えても、しっかりと飛び出てくれています。
装着の際も、マイナスドライバー一本でBFピンと通常ピンの交換ができます。
リキッドの出口
リキッドの出口は非常に確認しにくいですが、デッキの隙間からなんとか確認できます。
デッキの下から出てきて横に流れていく導線が想像できます。
粘度が高いリキッドでも真ん中の穴からデッキの上に出てきて横に流れていきそうな感じがします。
BFピンの長さがデッキに比べて低い位置にありますから、デッキ内に残ったリキッドはしっかりと吸い戻してくれると思います。
Alexander RDAトップキャップ裏
トップキャップとチャンバーを一緒に紹介しないと、このAlexander RDAの特徴が紹介しきれません。
トップキャップだけを見てみると、ドリチとのクリアランスもよくないですし、変な段差も生まれています。
Alexander RDAの場合は、トップキャップはエアフローの調整が主な仕事です。

チャンバーパーツと組わせて使用することにより、チャンバーパーツとトップキャップが一体となった形になります。
トップキャップは再度バレルパーツのOリングで固定される形となります。

このようにトップキャップとチャンバーパーツが一体化して初めて美しいドーム型に仕上がります。
他のRDAなどと比べてみても、アールのかかり方が緩やかになっている印象を受けます。
ゆっくりと傾斜がかかっていることにより、デッキ内で対流が発生しにくくなっており、スムーズなミストの流れが期待できます。
Alexander RDAエアフロー

先ほどもご紹介したように、エアフロー調整はトップキャップが仕事をしています。
エアをトップから取り込み、インナーチャンバーとの隙間にあるハニカムエアフローを通ってデッキ内に入っていきます。
- 全開
- 左右半分開き
- 下半分開き
エアの調整方法は左右で半分に調整したり、上下で調整したり、かなりカスタマイズ性に富んでいます。
上部の1つだけを締めて、「3/4開け」なんていう開け方もできます。

ただし、最終的にはインナーチャンバーのハニカムエアフローを通ってコイルにエアが当たりますので、コイルの一部分を狙ってエアを充てるということは苦手な印象。
どうしてもハニカムエアフローの面でエアを当てるような仕組みとなります。
Alexander RDAデッキ構造

Kaees曰く”Lotus-leaf shape post-less deck(蓮の葉型のポストレスデッキ)”です。
蓮の葉というのは、分かりやすく言うなら『となりのトトロ』のトトロが傘として持っている葉っぱのことです。
蓮の葉の形にしていることで期待できる効果はあまりなさそうですが、ビルド自体はデトラビのようなビルドができそうです。

イモネジとデッキの隙間もなく、また、デッキ側にもイモネジの山が確認できます。
このため、ワイヤーがイモネジの横に入り込んでしまう可能性を軽減することができます。
Alexander RDAビルドしてみました

コイルレッグの長さは、クラプトン系コイルを使うかシンプルなラウンドワイヤーを使用するかや、好みによっても大きく変わります。
私のレビューでは、とりあえずラウンドワイヤーの0.5Ωで組んでから特徴をつかみたいという思いがありますので、まずは26Gの単線ビルドでレビューします。
ということで、コイルレッグの長さは6mmにカット。

ビルドそのものは非常に簡単で、コイルを置いてイモネジを締めるだけで大丈夫。
コイルレッグが逃げたりなんだったりということは一切ありません。

コイルジグを通して、エアが垂直にコイルに当たるように成形します。
6mmだと結構高い位置に来ますし、チャンバー上部がドーム型になっていますから、キャップと接触していないか確認するために一度キャップを取り付けてみます。

いい感じにコイルにエアがぶち当たりそうな気がします。
どうしても『面』でエアを充てる構造となりますので、コイル幅はできるだけエアフローの幅に合わせてあげるようにビルドしてあげるのがベター。

いつものように0.5Ωを目指してビルドしたのですが、コイルレッグが長かったために少し高めの0.57Ω。
まぁ許容範囲の抵抗値のブレということにしましょう。
ウィッキング

コイルレッグが6mmと長いことに加え、ウェルも深いですからかなり長めにコットンを残します。
ここまでコットンを残すとなると、コットンの性能もいいものを使用したほうがいいと思います。

ふんわり横に落としてあげて完成。
この状態だと、本当にDead Rabbit RDAのように見えてきます。
Alexander RDA実際に使ってみて
デドラビの後継機のひとつとして
【悲報】永きに渡り皆様に愛されたウサギが、、、正式に製造終了との連絡を受けました。。残る在庫で終わりですので、迷っている方はお急ぎくださいませ💦 https://t.co/FWOeO3Dh3C#VAPE #ecig #flavorkitchen #電子タバコ #フレーバーキッチン #フレキチ #vape好きな人と繋がりたい pic.twitter.com/2r0EuztqiH
— 電子タバコ フレーバーキッチン (@FlavorKitchen) 2019年7月10日
Alexander RDAのレビューを考えているときに飛び込んできたビッグニュースが、デドラビの製造終了のお知らせ。
思い返してみれば、Dead Rabbit RDAのデッキが今のポストレスデッキのプロトタイプと言えるでしょう。
デドラビの良さはもう語りつくされていますが、ポストレスデッキのプロトタイプなりの改善点もありました。
ウェルが浅かったり、デッキとチャンバーパーツの切り欠きがなかったりなどの弱点を克服したRDAと言えば、このRDA良さが伝わるのではないでしょうか。
Dead Rabbit RDAの生産終了に伴って人気が再燃しています。
私自身もDead Rabbit RDAを持っており、Dead Rabbit RDA良さは分かっているつもりではあるのですが、「Dead Rabbit RDAかAlexander RDAかどちらかを選びなさい」と言われたら、私はAlexander RDAを選びます。