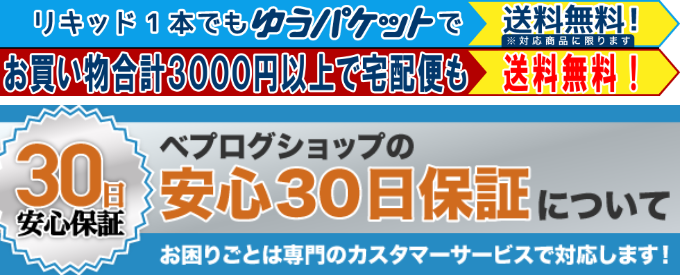あのデドラビの純血後継機、V2
VAPEの流行り廃りは数あれど、VAPEの流れを大きく変えたターニングポイント的なデッキや構造は数えるほどしかありません。
数年前のトレンドデッキと言えば、ベロシティースタイルという2ポールデッキでした。
その当時新しく発売されるアトマイザーのほとんどがベロシティースタイルのデッキだったように思います。
そのベロシティースタイルと同等かそれ以上に影響を与えたデッキと言えば、デッドラビットデッキ。
本家のデドラビが大ヒットを飾り、そのビルドの楽さやスコンカーにぴったりの構造が一世を風靡しました。
デドラビにインスパイアされたRDAは数えだしたらきりがないほどです。
そんな中、Dead Rabbitを製造・開発をしたHellvapeから正真正銘の後継機、Dead Rabbit V2が発売されました。
あまりにも似たようなデッキがたくさんありすぎて、それほど変わり映えしないのかなと思っていました。
ですが、実際に使用してみると細かな気配りや改善点がものすごくポイントの高い仕上がりになっていましたので、「いやいや、もう他のデトラビ系アトマと同じでしょ~?」と思っている方は、ちょっと覗いて行ってみてください。
Dead Rabbit V2 RDA付属品

- Dead Rabbit V2本体
- マニュアル
- マイナスドライバー
- 六角×2
- 交換用Oリング
- 交換用ドリップチップ
- 510変換アダプター
- BFピン
- イモネジ×4
- ステッカー
この時点で不思議に感じたのが、ドライバーが合計で3つも付属しているということ。
大きい六角はコンタクト交換用ということが分かるのですが、小さい六角とマイナスドライバーが両方ついています。
マイナスドライバーはRDAに最初から入っているイモネジ用、六角は交換用のイモネジ用ということでした。
マイナスネジだったり六角ネジだったりと、好みに応じて付け替えることができるのですが、潔く一方に合わせておいてくれた方がありがたかったかなと思います。
…これは前作と同じことを言っていますね。
Dead Rabbit V2 RDAポジティブピン
通常コンタクトピン(デフォルト)

コンタクトも飛び出ていますし、インシュレーターも目視できますので、メカニカルフレンドリーなコンタクトピン。
もちろん、メカニカルフレンドリーということはテクニカルMODでも問題なく利用できます。
BFピン

Dead Rabbitはスコンカー用RDAとして使用する人が多いかもしれませんが、スコンカーで使用するにはコンタクトピンの交換が必要です。
最初からBFピンを入れておいてほしいという人がいますが、やはりプリインストールされているピンは通常コンタクトである方がうっかりミスを減らせるというものです。
リキッドの出口

Dead Rabbit V2はデッキベースから少し高い位置に、そして横向きにリキッドの出口が置かれています。
これで多少のリキッドをRDA内に残しながら、かつコットンの方向へ効率的にリキッドチャージが可能となっています。
Dead Rabbit V1
前作はデッキベースとツライチの高さにリキッドの出口がありました。
余分なリキッドをほぼ全て吸い込んでくれる形になっていますが、コットンがリキッドを吸収する前に吸い込んでしまうこともあります。
個人的には、多少のリキッドはRDA内に残っているV2の形が好ましいと思います。
Dead Rabbit V2 RDAトップキャップ裏

美しい滑らかなドーム型のトップキャップとなっています。
そして、今ではほとんどのRDAについているノッチが確認できます。
この辺りの構造については、エアフローの項目で細かく触れてい行きたいと思います。
Dead Rabbit V2 RDAエアフロー

Dead Rabbitの特徴的な下向きのエアフローは健在です。
サイドとトップのパーツを交差させて空気の量を調整するタイプです。
- 穴なし
- ハニカム構造
エアフローで特に特徴的な部分と言えば、ハニカム構造が採用されたことでしょう。
今までも色々なインスパイア品でハニカムエアフロー構造が採用されていましたので、本家のV2でも採用される運びとなったようです。
ハニカム構造を取り入れたことにより、コイルにまんべんなくエアを当てることが可能になり、さらにドローもやや抵抗感を持たせることができるようになりました。
先ほど、サイドバレルのノッチの話をしましたが、ノッチの移動幅は90度あります。
さすがにコットンの横からエアを当てる人はいないと思いますが、この移動幅を持たせることによって可能になることがあります。

トップパーツとこのようなクリアランスで使用することにより、エアを絞りながらもコイルの正面からエアを当てることが可能になりました。
ノッチの位置がガチッと固定されているタイプだと、エアを絞ってもコイルにエアがきれいに当たらないという状態になることが多いです。
ノッチの移動幅を大きめに持たせることにより、エアの流したい量を、エアを流したい方向から当てることができるようになります。
Dead Rabbit V2 RDAデッキ構造

ではでは、少し変更点が加えられたデッキに焦点を当ててみたいと思います。
- Dead Rabbit V1
- Dead Rabbit V2
前作のものと比較すると、デトラビちゃんの耳に角度がつけられています。

この角度のおかげで、コイルレッグの処理が飛躍的にしやすくなりました。
ですが、こういうタイプのアトマイザーは最初にコイルレッグの処理をしてしまう方が一般的だと思います。

イモネジを開いていくと、かなり分厚いコイルでもドンと来いと言わんばかりのワイヤーホール。
クラプトンでもエイリアンでもガチッとホールドしてくれそう。
ただ、28G以下の単線ワイヤーだとネジ山の隙間に入ってしまうかな?
細いワイヤーのパラレルなんかでビルドするときなんかはコイルレッグを捻るなどの対処が必要だと思います。
ビルドしてみました

私自身はマイナスネジだろうが六角ネジだろうが好みはありませんので、そのままマイナスネジでビルドしていきます。
コイルを少し浮かせながらイモネジを締める必要がありますので、コイルジグなどを使用せずにフリーハンドの方がビルドは楽にできました。

余ったワイヤーですが、横からワイヤーカッターで処理することも可能。(その時は切れ端が変なところに行ってしまわないようにご注意を)
コイルレッグが反対側のポールや、デッキベースに触れてしまわないのであればそのまま放置でも構わないと思います。

コイルの高さはこれくらい。
デトラビ系アトマイザーはこれくらいのコイル位置が一番いいってジッちゃんが言ってた。

抵抗値はいつものように0.5Ω付近。(Ni80, 26G, 内径3mm, 10巻)
ウィッキング

デトラビちゃんは結構コイルまでの高さがありますので、長めのコイルレッグが必要。
供給不足にならないように、毛細管現象を最大限に活用できるようにコットンの端を梳く(繊維の量を少し減らしながら方向を整えること)作業をした方がいいです。

このちょっとだけ高くなっているデッキベースも秀逸な変更点です。
実際は、サイドバレルパーツのノッチの引っ掛かりとなる部分なのでしょうが、コットンレッグをデッキ内に収めておくという仕事も担ってくれています。
前作のデッキはウェルらしいウェルがなかったので、コットンレッグの収まりがよくありませんでした。
せっかくモフモフにしたコットンが、ちょっとした衝撃で流れてしまってウィッキングのやり直し…ということが起こりにくくなっています。
実際に使ってみて
スカスカから抵抗感を感じるドローまで調整幅の広いエアフロー
- 穴なし
- ハニカム構造
V1から大きく様変わりしたエアフローに最大級の賛辞を贈りたいと思います。
前作のデトラビは穴なしタイプのものがデュアル用とシングル用に開いているだけでした。
「絞っても絞ってもスッカスカ。ちょうどいいドローになったと思ったら、コイルに全然エアが当たってない…。しゃーねー、エアフローに合わせてビルドすっか」というよく分からない事態が発生していました。
いや、それでもいいならいいのですが、個人的にはビルドに合ったエアフローに調整したいじゃないですか。
Dead Rabbit V2では、その時のビルドに合わせたエアフローの調整が可能になりました。
これにより、私みたいな0.5Ωビルダーや海外YouTuberもびっくりの低抵抗ビルダーまで幅広いユーザーに対応するアトマイザーに進化しました。
絶妙な強度の違いのあるOリング

あくまで体感のお話ですが、Oリングの強度に微妙な変化がつけられているような気がします。
まず一番強いのはデッキベースの一番下のOリング。
これが比較的かなりガッチリとハマっていて、その直上にあるOリングの強度は少し弱めに設定されているように思います。
この強弱のついたOリング2つの作用で、リキッド漏れ防止&チャンバーパーツの向きが変わるのを防止しています。(洗浄後はリキッドを少し塗った方がいいかも)
もう1つのあるトップパーツのOリングは、強度で言えば『中』にというところでしょうか。
この『中』に設定されているおかげで、エアフロー調整が非常に快適に行うことができます。
「トップのエア調整をしようと思った時にサイドバレルも一緒に回ってしまう」ということが、こういった構造のRDAでよくあります。
ですが、Dead Rabbit V2はサイドバレルはボトムの『強』+『弱』=『強⁺』で固定されているので、一緒に回ってしまうということがありません。
エアフローの調整が非常に快適に行うことができますし、エアフローの調整が決まれば勝手に動いてしまうということもありません。
…分かりにくいので一言で簡単に説明すると、「Oリングの強度がカンペキ」ということです。
理にかなった細かな改善点
- ハニカム構造
- ポール
- ウェル
前作から大きな変更点はないものの、Dead Rabbitの細かな改善点を漏れなく改善しているDead Rabbit V2。

前作のデトラビが爆煙低抵抗VAPER向けという感じでしたので、そういった方は正直あまりV2の魅力はないのかもしれません。
Dead Rabbit V2は、それなりの抵抗値で、それなりのミストを楽しみがら、しっかりと味を味わいたい系VAPERに向けたフレーバーチェイスも可能になったと言えるでしょう。
それでいて、前作のような爆煙スカスカドローも楽しめる守備範囲の広いRDAへと変貌を遂げました。
P.S. 正月休みにこのアトマイザーを使っていたのですが、ものすごい味が出てリキッド消費量が段違いに増えました。
ここで買えます

※最近(2020年1月時)、Health Cabinさんの値段設定が最安値である可能性が非常に多いです。今までなんとなく嫌厭していた人も一度他のサイトと比較してみることをオススメします。